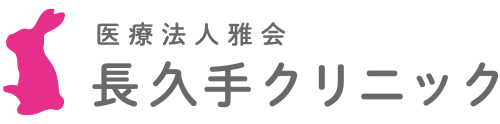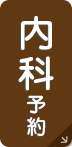施設基準について(歯科)
◆当院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生局に届出を行っています。【歯科】
・外来感染対策向上加算
・医療DX推進体制整備加算
・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
・歯科外来診療医療安全対策1
・歯科外来診療感染対策1
・慢性腎臓病透析予防指導管理料
・歯科治療時医療管
・小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
・在宅療養支援歯科診療所1
・在宅患者歯科治療時医療管理料
・地域医療連携体制加算
・在宅歯科医療推進加算
・有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査
・CT撮影及びMRI撮影
・歯科口腔リハビリテーション料2
・口腔粘膜処置
・歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算
・歯科技工士連携加算2
・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
・歯科技工加算1及び2
・歯周組織再生誘導手術
・レーザー機器加算
・クラウン・ブリッジ維持管理料
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)
◆ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準【歯初診】
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。
(5) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(6) 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
◆ 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)【医管】
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
ア 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
イ 酸素供給装置
ウ 救急蘇生セット
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
◆ 在宅患者歯科治療時医療管理【在歯管】
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2) 常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関が規定する常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) 当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
ア 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
イ 酸素供給装置
ウ 救急蘇生セット
(4) 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
◆ 地域医療連携体制加算【歯地連】
訪問診療に際し、地域医療連携体制の円滑な運営を図るべく、下記の病院や医院と連携し、緊急時の対応を確保しています。
(1) 診療所であること。
(2) 夜間、休日等における緊急時の体制を継続的に確保するため、歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関及びその他の歯科の保険医療機関との連携による地域医療支援体制を備えていること。
◆ 在宅歯科医療推進加算【在推進】
居宅等への訪問診療を推進しています。
(1) 歯科医療を担当する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該診療所で行われる歯科訪問診療の延べ患者数が月平均五人以上であって、そのうち六割以上の患者が歯科訪問診療1を算定していること。
◆ 在宅療養支援歯科診療所1・2【在援進】
当院では訪問診療を行っております。高齢者の在宅や社会福祉施設での療養を歯科医療面から支援するため、下記の病院や診療所、介護・福祉関係者と連携体制を整えています。
在宅療養支援歯科診療所1の施設基準
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計18 回以上算定していること。
イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
ウ 歯科衛生士が配置されていること。
エ 当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
オ 歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。
キ 以下のいずれか1つに該当すること。
(イ) 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に年1回以上出席していること。
(ロ) 過去1年間に、病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
(ハ) 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。
ク 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
(イ) 栄養サポートチーム等連携加算1又は2の算定があること。
(ロ) 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
(ハ) 退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること。
ケ 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(イ) 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。
(ロ) 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(ハ) 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
(ニ) 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
(ホ) 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
① 区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20 回以上であること。
② 区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20 回以上であること。
③ 区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理及び区分番号「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40 回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
コ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
在宅療養支援歯科診療所2の施設基準
次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計4回以上算定していること。
イ (1)のイからカまで及びケのいずれにも該当すること。
ウ 年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
◆ 歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準【外安全】
当院では安全で良質な医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、十分な装置・器具を有しております。
自動体外式除細動器(AED)を設置しており、医療安全に配慮しています。
医療安全管理対策など、各種の医療安全に関する指針を備えています。
患者さんの搬送先として下記の病院と提携し、緊急時の体制を整えています。
または歯科外来診療における医療安全対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、
研修を受けた歯科医師が常勤し、職員に医療安全対策に係る院内研修等を実施しています。
また、緊急時には下記の医療機関と連携を取り、適切に対処を行える体制を整えています。
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
エ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
オ 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(イ) 自動体外式除細動器(AED)
(ロ) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(ハ) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(ニ) 血圧計
(ホ) 救急蘇生セット
カ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
キ 以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(ロ) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
ク 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
ケ クの掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
◆ 口腔管理体制強化加算の施設基準【口菅強】
小児から高齢者まで幅広い口腔機能の管理や歯の病気の重症化予防を含む 継続的な歯科治
療管理をしていきます。 AED などを配置し、より安心で安全な歯科医療環境を提供しています。
または歯科疾患の重症化予防に資する継続管理、高齢者・小児の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。
01 歯科医師が2人以上いる、または歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1人以上いる。
02 次のいずれにも該当すること。
・ 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)または (Ⅱ)を合わせて30回以上算定していること。
・ 過去1年間にフッ化物塗布処置、または歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算を合わせて10 回以上算定していること。
・ クラウン、ブリッジ維持管理料を算定することを届け出ていること。
・ 歯科点数表の初診料注1に規定されている施設基準を届け出ていること。
03 口腔機能管理に関する実績があること。
04 次のいずれかに該当すること。
・ 過去1年間で、歯科訪問診療1もしくは 2の算定回数、または連携する在宅療養支援歯科診療所1または2に依頼した歯科訪
問診療の回数が合わせて5回以上であること。
・ 過去1年間で、診療情報提供料または診療情報連携共有料を合わせて5回以上算定している実績があること。
・ 在宅歯科医療に係る連携体制が確保されていること。
・ 歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修、小児の心身の特性、高齢者の心身の特性および緊急時対応等の適切
な研修を修了した歯科医師が1名以上いること。
・ 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応できるように、別の医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
05 歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名・診
療可能日・緊急時の注意事項等について、事前に患者または家族に対して説明の上、文書により提供していること。
06 基準5の歯科医師が次の3つ以上の項目に該当すること。
・ 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
・ 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
・ 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
・ 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
・ 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1または栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
・ 在宅医療または介護に関する研修を受講していること。
・ 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、
在宅患者連携指導料または在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
・ 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
・ 自治体が実施する事業に協力していること。
・ 学校医等に就任していること。
・ 過去1年間に、歯科診療特別対応加算や初診時歯科診療導入加算を算定していること。
07 歯科用吸引装置などを使い、診療台ごとに診療中に飛び散る細かい物質を吸引できるようになっている。
08 患者にとって安心で安全な歯科医療環境を提供できるように次の装置・器具などをしっかりと使用している。
・ 自動体外式除細動器(AED)
・ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・ 酸素供給装置
・ 血圧計
・ 救急蘇生セット
・ 歯科用吸引装置
◆ 歯科外来診療感染対策加算1に関する施設基準【外感染1】
歯科用吸引装置等を備え、歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を整えています。
院内感染管理者を配置し、院内感染防止対策についての体制整備を行っています。
または歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、
研修を受けた者が常勤し、院内感染防止に努めています。
ア 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
◆ 明細書発行体制等加算【明細書】
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
なお、必要のない場合にはお申し出ください。
または領収証の発行とあわせて、明細書の発行を(公費負担医療受給者で医療費の自己負担がない方にも)無料で行っております。必要がない方はお申し出下さい。
または当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は同令附則第三条の二に規定する光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
◆ 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査に関する施設基準【咀嚼能力】
義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分
析装置または歯科用咬合力計を備えています。
(1) 有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準
次のいずれにも該当すること。
ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
(2) 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準
次のいずれにも該当すること。
ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ 当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。
(3) 有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準
次のいずれにも該当すること。
ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び歯科用咬合力計を備えていること。
(4) 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査の施設基準
次のいずれにも該当すること。
ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
イ 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。
◆ 顎関節症の歯科口腔リハビリ(歯科口腔リハビリテーション料2)【歯リハ2】
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。
または顎関節症の治療用装置を作製し、口腔リハビリを実施しています。
◆ 口腔粘膜処置【口腔粘膜】
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。
◆ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー【歯CAD】
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
または歯科用CAD/CAM 装置(コンピューター支援設計·製造ユニット)を用いて、白色の冠などを作製しています。対象など条件がありますので詳しくはご相談下さい。
またはコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、前歯・臼歯に対して歯冠補綴物を設計・製作しています。
※金属アレルギーの方はご相談ください。
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。
◆ 歯科技工1・2【歯技工】
院内に歯科技工士がおりますので、迅速に義歯(入れ歯)の修復及び、内面適合法(軟質材料)を行います。
◆ 歯周組織再生誘導手術【GTR】
重度の歯周病により歯槽骨が吸収した部位に対して、特殊な保護膜を使用して歯槽骨の再生を促進する手術を行っています。
歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。
◆ レーザー機器加算【手光機】
口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。
(1)当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する医師又は歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
◆ クラウン・ブリッジの維持管理料【補菅】
装着した冠(かぶせ物、詰め物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
または当院で装着した歯冠補綴物(チタン冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠)、ブリッジについて、2年間の維持管理に取り組んでいます。(24年6月現在)異常があればそのままにせずお早めにお知らせください。