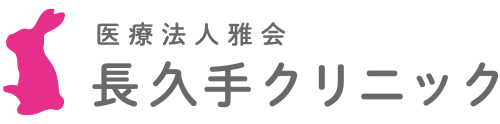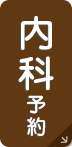【免疫が暴走するとき】
私たちの体には「免疫」と呼ばれる仕組みがあります。
「免疫」は、いったんかかった感染症にもう一度かからないように抵抗力を獲得する仕組みのことです。はしかや風しんに一度かかると、通常は二度と同じ病気にならないなどが有名です。
ワクチンは、この免疫の働きを利用したものです。弱い毒性の微生物(病原体)をあらかじめ体に入れることで、本来の強い毒性の微生物が侵入したときに、体がしっかり抵抗できるようにしてくれます。
ところが、この免疫システムが何らかのきっかけで「自分自身の組織」を攻撃してしまう場合があります。これを「自己免疫」といい、自己免疫によって起こる病気を「自己免疫疾患」と呼びます。
🐰よく「関節リウマチ」は「膠原病(こうげんびょう)」ですか?と聞かれますが、「自己免疫疾患」の中の「膠原病」の中の「関節リウマチ」という分類が一般的です。
🐰ただし、「関節リウマチ」は「関節リウマチ以外の膠原病」に比べ患者さんも多く治療も進歩しているので、別の扱いにしていることも多いです。
・ある特定の臓器だけが攻撃される場合は、「臓器特異的自己免疫疾患」と呼ばれ、1型糖尿病(インスリン依存型糖尿病)やバセドウ病、クローン病などが当てはまります。
・また、微生物ではなく少量の環境物質を敵とみなして攻撃してしまう場合を「アレルギー」といい、花粉症やアトピー性皮膚炎などが代表的です。
いずれも免疫が行きすぎて暴走してしまう点は共通しています。微生物を攻撃する場合は、微生物を排除できれば戦いは終わりますが、「自己」を相手に戦いが始まった場合は、自分の組織を破壊し尽くすまで戦いが続いてしまうという厄介な特徴があります。
🐰「自己抗体」という自分の体を攻撃する抗体が存在することは、自己免疫疾患の証明になっています。
🐰全身性エリテマトーデス(SLE)のような、体の様々な臓器が傷害される全身性免疫疾患(膠原病)では、「抗核抗体(こうかくこうたい)」のような自分自身のあらゆる組織に存在する細胞成分(細胞核)に対する抗体が存在します。
🐰ある特定の臓器だけが攻撃される「臓器特異的自己免疫疾患」である1型糖尿病やバセドウ病では、膵臓や甲状腺などの特定の臓器に対する自己抗体が血液中に存在します。
【なぜ自己免疫が起こるのか?】
様々な感染症(ウイルスや細菌など)のほか、環境中の物質が免疫を活性化させ、自己免疫が引き起こされるきっかけになることがあります。
代表例が歯周病です。
歯周病は、お口の中に潜む菌が慢性的に炎症を起こし、免疫系を刺激し続ける原因となります。関節リウマチなどの自己免疫疾患に影響すると言われています。
🐰長久手クリニックでは歯科開業当初から「お口もとから健康を」を理念として歯周病に取り組んでいます。内科併設された今でもこの理念は変わっていません
一方、感染症だけでなく、過剰な紫外線を浴びた皮膚に炎症が起こったり、分解されにくい粉じん(ふんじん)やPM2.5を吸い込んだりすることでも、免疫が過剰に反応することがあります。
実際に、大震災のがれきの粉じんを吸引した後に、ANCA関連血管炎などの自己免疫疾患が増えたという報告もあります。
このように、微生物由来であれ環境物質であれ、体が「危険だ」と判断すれば、免疫を活性化させてしまい、自己免疫疾患のきっかけになるのです。
【どんな人が自己免疫性疾患の発症に注意すべきか?】
・家族に自己免疫疾患の方がいる場合血縁に膠原病など自己免疫疾患の方がいらっしゃる場合は、遺伝的に自己免疫リスクを持っている可能性があります。
ご自身が発症しなくても、遺伝子が受け継がれていることがあります。
・そうでない方も注意が必要
家族歴がなくても、偶然リスク遺伝子を両親から受け継ぎ、自分だけが発症するケースもあります。
まったく病気と無縁に見えても、自己免疫疾患が突然起こることがあるので、誰にでも可能性はあるといえます。
【遺伝子だけが全てではなく「環境」が関わる】
全く一緒の遺伝子をもつ一卵性双生児が、同じ自己免疫疾患を発症する確率は、3 ~ 4 割程度です。すなわち遺伝子だけではすべては決まりません。
「環境」が関わります。
【「環境」幼少期と免疫の発達】
幼いころにいろいろな微生物や環境に触れ合うことで、免疫は「敵」を見分ける訓練をし、免疫が必要以上に反応しない仕組み(免疫寛容)を身につけていくと考えられています。
これは「衛生仮説」と呼ばれる考え方で、あまりにも清潔すぎる環境で育つと、逆に免疫が過剰に反応しやすくなる可能性が示唆されています。
幼少期に多様な微生物に触れる経験を重ねるほど、免疫はバランスを保つ訓練を受けていると考えられます。
5歳未満の小さなお子さんほど、こうした「免疫の学習」の影響は大きいとされています。
【「環境」5歳以降と腸内環境の重要性】
5歳を過ぎても、腸内細菌叢(腸内フローラ)のバランスを整えることで免疫を良好に保つことができる可能性があります。
たとえば、麹や納豆や漬物、味噌などの発酵食品を適度に摂ることは有効かもしれません。
さらに、野菜や果物など食物繊維をしっかり取り入れることで、腸内細菌の多様性が保たれ、免疫が過剰に反応しにくくなると考えられています。
重要なのは、腸内細菌の多様性です。あまり「絶対にこうしなければ」と神経質になりすぎず、多様な食生活を楽しむことが大切です。
【「環境」ストレス】
ストレスも免疫のバランスを乱す大きな要因になります。仕事や人間関係など、さまざまなストレス源がありますが、不自然なほどのストレスにはできるだけ距離を置く、逃げる必要があります。
適度な運動や十分な睡眠、趣味の時間を持っていきましょう。
🐰そうは言っても、難しいですよね...
【「環境」喫煙や歯周病】
禁煙や歯周病治療を行いましょう。
【再度のまとめ】
日常生活の中で、感染症の予防はもちろん大切ですが、過剰に清潔すぎる環境を作ったり、ストレスが溜まりすぎたりすることにも気を配り、バランスを意識した生活を心がけましょう。
🐰とにかくやりすぎは禁物です。不安になりすぎない、考えすぎないようにしましょうね🐰
以上が、「免疫の暴走(自己免疫疾患)」とその予防の考え方の一つです、結論と正解はありません。
ご自身やご家族の健康管理にお役立ていただければ幸いです。
膠原病や関節リウマチの早期診断と皆様のご不安がとれるのがわたしたち長久手クリニックの願いです。